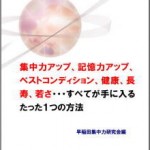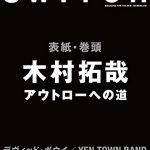- 2025-3-24
- 人間関係・友人関係
こんにちは、中西です。
前回は、「お金よりも時間を重視」する価値観を持っている人の方が、
仕事などで「やりがいのある活動」に取り組む傾向が強くなり、結果として幸福感がアップする
…というハーバード大学の研究をご紹介しました。
今回はこの流れで、幸福感アップに関わる重要なホルモンの“新しい仕組み”が解明された研究をご紹介します。
今回テーマとなるのは、幸せホルモンのひとつ、オキシトシンです。
オキシトシンは有名なのでご存じの方も多いと思いますが、幸せホルモンであり、愛情ホルモンとも言われています。
最初に発見されたのは、お母さんが赤ちゃんに授乳中、脳内で分泌されていたことからでした。
人との関係に関わるホルモンでもあるので、絆ホルモンとも呼ばれています。
今回はこのオキシトシンの新たな発見ですが、結論から言いますと、
【 「孤独な状態」が続くと、脳からオキシトシンが減少し、肝臓の働きが落ちて、不健康になりやすい 】
ということが判明しました。
※参考:本記事下部に記載
これは慶應大学の医学部が2024年12月に発表した研究です。
もともと、人とのつながりが少ない社会的孤独が、心の問題だけでなく、動脈硬化や心臓病などのリスクを高めることが先行研究で判明していました。
ただ、なぜ孤独がそのような状態を引き起こし、体に悪いのか、その具体的な仕組みは不明だったようです。
そこで、今回の研究では、マウスを使った実験が行われました。
絆が深い兄弟のマウスを使って、1匹ずつ隔離して社会的孤独の状態を作り出し、変化を観察しました。
動脈硬化の進行、体内のホルモン、脂質代謝などの変化を調べたようです。
その結果、脳の視床下部から分泌されるこのオキシトシンが、
孤独によって分泌が減少する
ことが分かりました。
まぁここまでは想定内の結果だと思われます。興味深いのは、そのオキシトシンの減少が
「肝臓に悪影響を及ぼす」
ことも判明したことです。
これは非常に興味深い発見だと思います。
肝臓にオキシトシンを受け取るアンテナ(受容体)があることが分かり、オキシトシンが肝臓にも届いて働いていることが判明した、ということです。
肝臓は食べ物から吸収した脂(あぶら)やコレステロールを整理・処理する工場のような臓器で、脂質のバランスを保つ大事な役割があります。
この肝臓に「オキシトシンを受け取る仕組み」が存在していたわけで、
そのオキシトシンが孤独によって減少することで、肝臓がうまく働かなくなるということです。
おそらく、肝臓の燃料が無くなるようなイメージかなと。
結果、孤独によって肝臓の機能が衰えて、脂質をうまく処理できなくなります。
オキシトシンは肝臓に対して、
・悪玉コレステロールを外に出す準備をする
・中性脂肪を分解しやすくする
という2つの良い働きをしているようなのですが、
孤独によってオキシトシンが減ると、この肝臓の働きがうまく機能しなくなる・鈍くなるということです。
結果として、肝臓が脂をうまく処理できなくなって、中性脂肪や悪玉コレステロールが増える。
その結果、血管が詰まって動脈硬化という血管の病気にもなりやすくなるというわけです。
つまり、
孤独な状態が続く
↓
脳から出るオキシトシンが減る
↓
肝臓の働きが落ちる
↓
脂が溜まりやすくなる
↓
血管の病気になりやすくなる
太りやすくなる
こんな流れになっているわけですね。
孤独が体に悪い影響を与えるということは以前からわかっていましたが、
今回の研究では、極めて具体的にどのように悪く作用するかが判明し、それが内臓である肝臓だったというのは、非常に興味深いと思います。
逆に言うと、人とのつながりがあると、絆ホルモン・愛情ホルモンであるオキシトシンが増えて、
肝臓が元気になり、その結果、脂質も溜まりにくく血管も健康になるということですね。
つまり、人との愛情や絆というのは、血管の病気を防ぐ薬のようなものとも言えます。
人とつながっていたり、愛情を注いでオキシトシンが分泌されていると、幸福感がアップするのはもちろんのこと、
実は肝臓が元気に働いて健康になっている、ということですね。
というわけで、肝臓から元気がなくなってうまく働かなくなり、脂肪が増えて太ってしまったり、血管が詰まって動脈硬化などになりたくないなら、
幸福感アップと言う心の観点だけでなく、健康という肉体の観点においても、
人とのつながりは大事にしなければいけない
ということになりそうです。
※参考「社会的孤独が動脈硬化を促進する仕組みを解明
-“絆”によって生まれるオキシトシンの健康メリットの新事実」慶應大学
https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/files/2024/12/16/241216-3.pdf

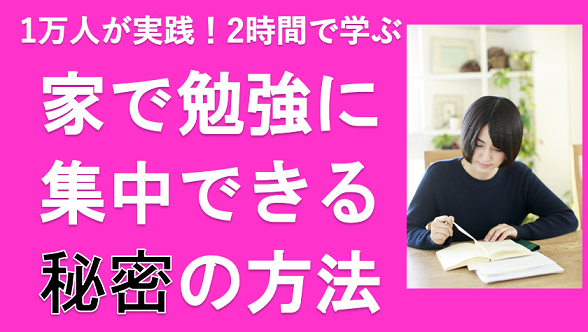
 感謝!YouTube動画が500万再生を突破!
感謝!YouTube動画が500万再生を突破!